ゼミ活動・進路・指導学生の論文タイトル
ゼミの活動
・2018年4月以降から現在
主なゼミの活動はX(旧Twitter)をみてください
・2017年8月
箱根でゼミ合宿をしました。
・2017年6月
Niedenthal , P. M., & Ric,F. (2017). Psychology of Emotion. 2nd Ed. Psychology Press.
を読んでいます。
・2017年4月~5月
各自の興味のある,感情についての和書を読みました。
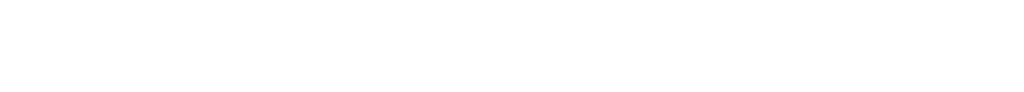
ゼミ生の進路
・大学院修了生の進路
京都外国語大学,山梨大学,国立教育政策研究所,小学校教諭,農林水産省,文教大学,各種企業など
・学部卒業生の進路
国土交通省,小学校教諭,千葉県,各種企業,大阪大学など
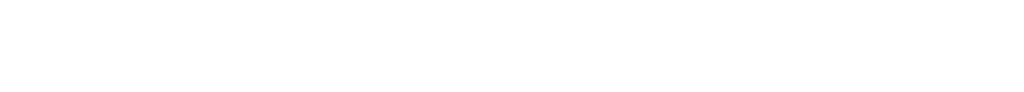
指導学生の論文タイトル
〇早稲田大学での指導学生の論文
| 年度 | 氏名 | 論文 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 坂元 花伽 | 修論 | 自閉スペクトラム症児の情動制御方略とメタ情動との関連―放課後等デイサービスにおける参与観察― |
| 2024 | 卒論 | 大学進学にむけての動機づけおよび親の自律支援行動からの学校適応感への影響 | |
| 2023 | 飯田凜 | 卒論 | 自己の不安定性とSNS依存の関係 |
| 2022 | 卒論 | 大学受験の学習計画の立案と実行機能の関連 | |
| 2022 | 吉江美萌 | 卒論 | 中学生においてBig Five は対人ストレス コーピングと精神的健康の関連に調整効果を及ぼすか |
| 2021 | 山本琢俟 | 博論 | 向社会的行動の発達的変化に対する 向社会的動機づけからの説明の試み ――児童期後期から青年期初期を対象に―― |
| 2021 | 長谷川朱音 | 修論 | 自傷行為と認知的感情制御方略・時間的展望との 関連-自傷行為の種類・分類に着目して- |
| 2021 | 板倉和輝 | 修論 | 達成目標と動機づけ調整方略が学習の持続性に及ぼす影響 |
| 2021 | 坂元花伽 | 卒論 | モデルの自己開示が被開示者の自己効力に与える影響 |
| 2020 | 菊池萌恵 | 卒論 | 基本的心理欲求が自己愛に及ぼす影響 ―自己愛による自己調整プロセスの検討― |
| 2020 | 長谷川あかね | 卒論 | 過剰適応における評価認識と構造モデル |
| 2019 | 福島健太郎 | 卒論 | 共感性が表情認知に与える影響について |
| 2019 | 長谷川朱音 | 卒論 | 大学生の回想する養育認知がレジリエンス要因に与える 影響 |
| 2018 | 錫木真裕子 | 卒論 | 愛着スタイルがレジリエンスに及ぼす影響 |
| 2018 | 竹花紀俊 | 卒論 | 大学生の学習動機づけとWork avoidance |

〇前任校での指導学生の修士論文・卒論論文
| 年度 | 論文 | テーマ |
|---|---|---|
| 2016 | 修論 | 日本語版Work avoidance目標尺度の作成と Work avoidance目標がWell-beingに与える影響 |
| 2016 | 修論 | 青年期の愛着がキャリア発達に与える影響 |
| 2016 | 修論 | 環境資源が二次元レジリエンス要因に与える影響 |
| 2016 | 修論 | 動機づけの転移―学習への動機づけに個人の趣味が与える影響― |
| 2016 | 卒論 | 互恵性規範が貢献感・心理的負債感と援助要請に及ぼす影響 |
| 2016 | 卒論 | 愛着が他者認知およびネガティブな感情経験の開示に与える影響 |
| 2016 | 卒論 | 公正世界信念と自己愛が被害者非難を媒介して感情に及ぼす影響 |
| 2016 | 卒論 | 英語に対する課題価値が学習方略・自己評価に及ぼす影響 |
| 2016 | 卒論 | 青ペンの使用が課題集中に及ぼす影響 Implicit Association Test(IAT)を用いた色嗜好との関連 |
| 2015 | 卒論 | 友人との学習が動機づけ調整方略及び学習パフォーマンスに与える影響についての研究 |
| 2015 | 卒論 | 児童と青年期の過剰適応の関係―教師の態度が及ぼす影響― |
| 2015 | 卒論 | 競技スポーツにおけるチームの動機づけ雰囲気が選手の目標志向性に及ぼす影響 |
| 2015 | 卒論 | ITCが英語学習者に与える動機づけ―課題価値理論を基に― |
| 2014 | 卒論 | 幼児期における愛着スタイルが青年期における自己開示に及ぼす影響 |
| 2014 | 卒論 | 感情への評価,感情表出の制御及び精神的健康との関連 ~制御を行う相手の親密度の違いに着目して~ |
| 2014 | 修論 | 日本の大学生の自尊心の変動性と将来への期待との関連 |
| 2014 | 修論 | 男子小学生における向社会的行動に対する認知 |
| 2014 | 修論 | 「中一ギャップ」によって生徒に生じる不安はどのように変化するか―有機体発達理論に着目して― |
| 2014 | 修論 | 対人恐怖心性―自己愛傾向2次元モデルと有能感類型の関連 ―顕在的・潜在的指標を用いて― |
| 2013 | 卒論 | 対人不安・緊張と身嗜みの関係 |
| 2013 | 卒論 | 性格特性とアンダーマイニング効果との関係 |
| 2013 | 卒論 | 情動特性、対人ストレスコーピングと精神的健康との関連 |
| 2013 | 卒論 | 運動部部活動生の学習に対する課題価値と部活動に対する動機の関連 |
| 2013 | 卒論 | 対人コミュニケーションにおける非言語情報の有用性 |
| 2013 | 卒論 | 現状維持効果の規定因~意思決定の際の感情に着目して~ |
| 2013 | 修論 | 潜在的な自己制御システムを測定するGo / No-go Association Task (GNAT) の作成 |
| 2012 | 卒論 | 留年学生の自我同一性―不適応観を超えて― |
| 2012 | 卒論 | 様々な活動場面におけるフロー体験と性格特性との関係 |
| 2012 | 卒論 | 自尊感情の不安定性と情動制御の関連 |
| 2012 | 卒論 | ポジティブ感情が衝動購買に及ぼす影響 |
| 2012 | 卒論 | 妬みがシャーデンフロイデに及ぼす影響 |
| 2012 | 修論 | 潜在的な愛着の内的作業モデルが情報処理に及ぼす影響―Go / No-go Association Task と語彙判断課題を用いて― |
| 2012 | 修論 | 高等学校における外国語不安に関するエスノグラフィー |
| 2011 | 卒論 | 感情の喚起が購買意欲に及ぼす影響-ポジティブ感情と評価サイトに着目して- |
| 2011 | 卒論 | 服装の色が印象形成に及ぼす影響 |
| 2011 | 修論 | 子どもの感情制御に絡む教師の働きかけ―小学3年生の教室における教師と児童の相互作用の分析― |
| 2010 | 卒論 | 表情操作が気分と内発的動機づけに及ぼす影響 |
| 2010 | 卒論 | 計算課題の遂行に及ぼすBGMの影響について-被験者の選好の視点から- |
| 2010 | 卒論 | 自己開示場面における開示抵抗感と愛着スタイルの関連 |
| 2010 | 卒論 | フィードバックとしての言葉かけが達成関連感情に与える影響―達成目標理論の視座から― |
| 2010 | 卒論 | きょうだいの有無ときょうだい関係-日常生活での相談への影響及び個人の性格特性との関連- |
| 2010 | 修論 | 一斉授業の構成において教師の権力はどのように機能するか-小学校道徳の授業における教師のリヴォイシング方略に着目して― |
| 2010 | 修論 | 教師の応答が児童の思考に与える影響について ~道徳の時間を通して~ |
| 2009 | 卒論 | 予期不安の発生に関する素因ストレスモデルの検討 |
| 2009 | 卒論 | 能力比較情報が協同問題解決の発話に及ぼす影響~他のグループとの比較を通じて~ |
| 2009 | 卒論 | 日本語版 アイデンティティ・スタイル尺度の妥当性の研究 |
| 2009 | 卒論 | きょうだい関係の移行プロセスに関する研究-青年期の心理的自立との関連から- |
| 2009 | 卒論 | 対人的葛藤事態における情動と青年期の愛着との関連 |
| 2009 | 修論 | 類推的問題解決における作図の有効性~抽象化構成に及ぼす影響~ |
| 2008 | 卒論 | 罪悪感、羞恥心と性役割意識の関係 |
| 2008 | 卒論 | 過程シミュレーションが自我関与の低い課題遂行に及ぼす影響について |
| 2008 | 卒論 | リズムダンス指導に関する質的研究 |
| 2008 | 卒論 | 大学生の仲間関係がソーシャルサポートとリスクテイキングに及ぼす影響 |
| 2008 | 修論 | 学校における児童の援助要請と対人関係の関連 |
| 2008 | 修論 | IATを用いた暗黙の知能観の査定と予測的妥当性の検討 |
| 2007 | 卒論 | 達成目標理論におけるIATの有用性の検討 |
| 2007 | 卒論 | 学習観が学習方略の選択及び学習活動に及ぼす影響 |
| 2007 | 卒論 | 算数文章題解決に及ぼすメタ認知的指導の効果 |
| 2007 | 修論 | MLTにおけるトレーナーの発話とメンバーの自己変容の検討 |
| 2006 | 卒論 | 自我関与が思考抑制の効果に及ぼす影響 |
| 2006 | 修論 | 達成目標理論の再検討-知能観および目標志向性の潜在的測定- |
| 2003 | 卒論 | 青年期の自己敵意の研究 |
| 2003 | 卒論 | 不安の覚知と情動知性・コーピングの関連について |
| 2003 | 卒論 | 小学生における達成目標と回避行動の関係 |
| 2003 | 卒論 | 環境移行に伴う児童の意識変化 |
| 2003 | 卒論 | 自己制御学習方略と達成目標・学習の価値との関係 |
| 2002 | 研究報告 | 「生きる力」を育む教育のあり方 |
| 2002 | 卒論 | 子どものどのような言動を手がかりに教師は児童理解に務めるのか |
| 2002 | 卒論 | 小学校で「遊びの先生」として関わる意味と限界 |
| 2002 | 卒論 | 他者評価が自己意識的情動におよぼす影響ー公的自己意識との関係から |
| 2002 | 卒論 | 友人関係における怒りの表出方法 |
| 2002 | 修論 | ネガティブ・ポジティブな気分,情動が推論に与える影響 |
| 2001 | 卒論 | 嫉妬の経験状態とメタ情動が情動制御に与える影響 |
| 2001 | 卒論 | 態度の類似性が友人間の親密度に及ぼす影響 |
| 2000 | 卒論 | 上位目標に対する下位目標の明確な設定が進路決定自己効力に及ぼす効果 |
| 2000 | 卒論 | 励ましの言葉と性格特性が情動制御に及ぼす影響 |
| 2000 | 修論 | 情動制御は学習の取り込みにどのように影響を及ぼすか? |
| 1999 | 卒論 | 青年期の怒りの研究:怒り・自己敵意・悲しみの関係 |
| 1999 | 修論 | 水平性概念の理解の発達 |